甲子園のアルプス席に立つと、ふと大分の潮風の匂いがした。昭和、平成、令和──時代は移り変わっても、背番号の汗の温度だけはどこか変わらない。僕は何度もその匂いを感じてきた。グラウンドの白線がまだ手描きだった頃も、スタンドの旗が焼けるように揺れていた頃も、いつも大分の球児たちはその風を連れて甲子園にやってきた。
1931年、大分商業が初めて全国の舞台に立った。1972年、津久見高校がついに全国制覇を果たした。2007年、楊志館が“無名校”のまま19戦無敗でベスト8にたどり着いた。そして令和のいま、明豊が新しい時代を切り開いている。
彼らの戦いには、決して派手さはない。だが、どの時代の球児にも共通していたものがひとつある。「大分の野球は、誰の真似でもない」という誇りだ。ここでは、そんな大分代表たちの歩みを、昭和から令和まで時代ごとに辿っていく。
第1章|大分代表の原点──大分商と戦前・戦後の甲子園
大分県が初めて甲子園の土を踏んだのは、1931年(第17回全国中等学校優勝野球大会)。代表校は、大分商業──大分の野球史はここから大きく動き出すことになる。
当時は現在のように県単位ではなく「九州大会を勝ち抜いたチーム」が全国に進む形式。その中で大分商は、全国の強豪に伍して甲子園に到達した。大分県勢の長い旅路の“はじまりの夏”であり、これが後の高校野球文化の礎になった。
戦後に入ると、別府第一、臼杵、大分第二、大分城崎──県内の各地から代表校が顔を出すようになる。大分の高校野球が“地方文化”として根づき始めたのはこの頃だ。
僕が昔聞いた話だが、まだ外野席が芝生だった時代、臼杵の応援団が太鼓を担いで深夜の船で大阪入りしたという。当時の大分から甲子園への距離は、今よりずっと遠く、そして重かった。それでも球児たちは胸を張り、堂々と全国の強豪と渡り合った。
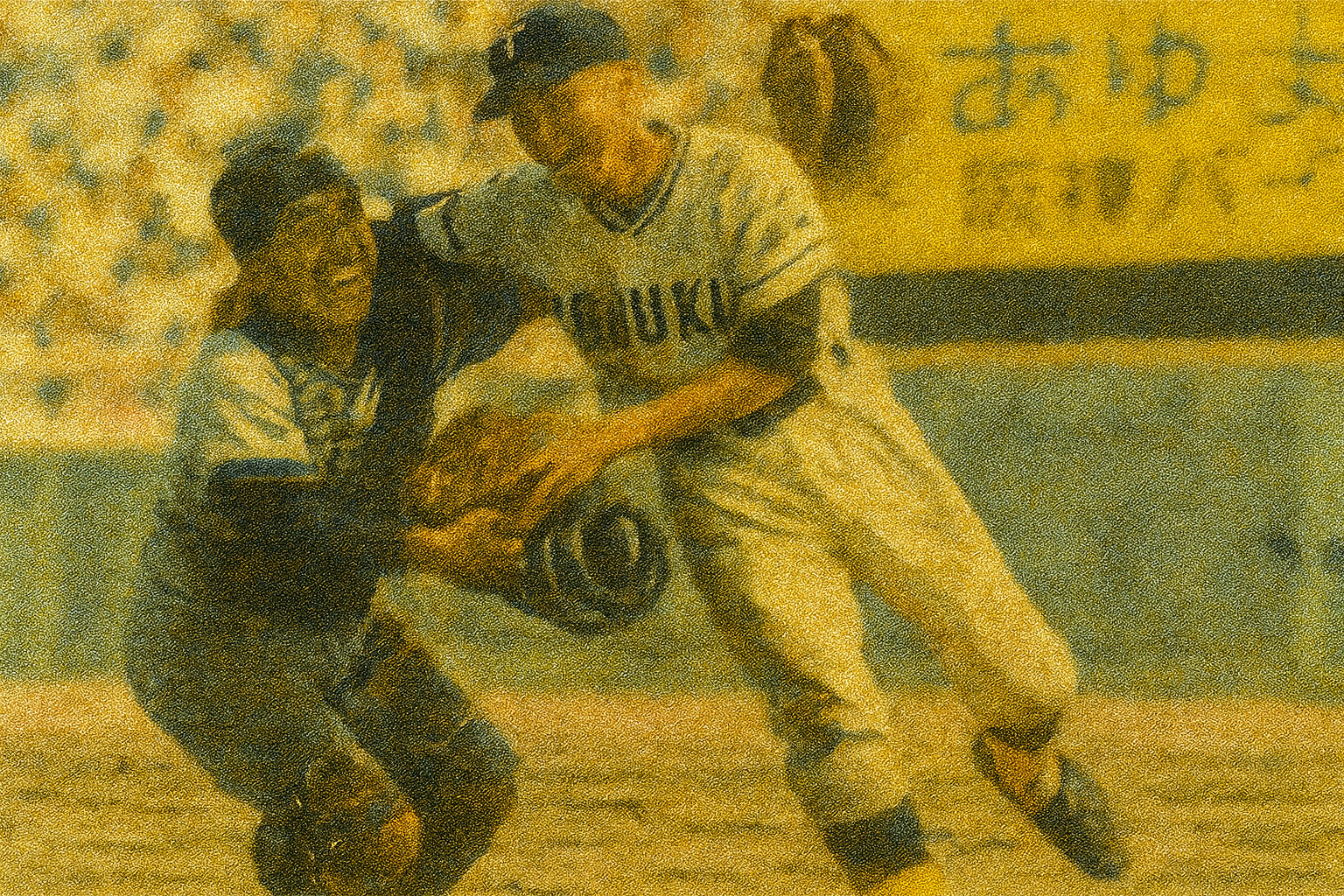
第2章|昭和の頂点──“津久見旋風”と全国制覇の夏(1972)
名将・小嶋仁八郎監督の哲学
昭和の大分野球を語るとき、誰もが口にする名前がある──小嶋仁八郎。津久見高校を率い、大分県勢初の全国制覇へ導いた“名伯楽”だ。
小嶋監督の指導は一言でいえば「生活そのもの」。グラウンド整備、挨拶、姿勢、泥まみれの練習。野球以前の部分で選手を鍛え上げ、試合では「個性を殺さず、伸ばす」ことを徹底した。
雨の日でも練習は止まらない。室内へ逃げ込むのではなく、あえて濡れた土でノックを続けた。泥だらけになりながら笑う選手の姿──津久見高校の“泥の強さ”の原点はここにあった。
水江—足立バッテリーの誕生と覚醒
1972年の津久見を象徴するのは、なんといっても水江投手と足立捕手のバッテリーだ。
水江のボールはキレというより「勢い」。腕を振り下ろすたび、風を切る音がスタンドに届くようだった。そして、その重く荒れる球を一歩も退かず受け続けたのが足立捕手だ。昭和らしい“身体で止める守り”は、チーム全体の信頼につながった。
当時の関係者は「水江—足立は、サインが短く、呼吸が合いすぎていた」と語る。小さな頷きひとつで投球が変わる──この独特の連携は、県大会から全国まで多くの強豪を封じ込めていく。
教え子が語る“小嶋イズム”──川崎憲次郎(元ヤクルト)による証言
1972年の主役が水江—足立だとすれば、その後の世代に“小嶋イズム”がどう受け継がれたのかを語れる存在がいる。
津久見高校出身で、プロ野球・ヤクルト、中日で活躍した川崎憲次郎だ。
川崎は自身のSNSで、こう振り返っている。
「県立高校を日本の頂点に2度も導いた大監督、小嶋仁八郎監督。
この方に憧れて津久見高校野球部に入部した人は多いハズ。
プロ野球選手も多数輩出、自分らの時は総監督。
『おい憲次郎、毎日300球投げ込め!45分間でな』
9秒に1球⚾️ 今では考えられないことも当時は当たり前、良き思い出です」
300球を45分──9秒に1球。数字だけ見ると過酷だが、川崎は「良き思い出です」と結ぶ。この“厳しさの中にある温かさ”こそ、小嶋監督が長年選手たちに与え続けたものだった。
1972年の水江—足立バッテリーが象徴した“勝負の呼吸”。
そして川崎憲次郎の世代が語る“人を育てる小嶋監督”。
このふたつが合わさって、津久見高校の伝統はさらに大きな物語となっていく。
1972年・あの夏の戦い──苫小牧工、明星、天理を撃破
津久見の快進撃はまさに“旋風”。初戦で苫小牧工、続いて大阪の明星、準決勝では天理という強豪を次々撃破していく。
当時のテレビ解説者が「荒削りだが魂を感じる」と評したように、津久見の野球は技術よりも熱量、そして水江—足立の気迫が色濃かった。
決勝・柳井戦──歴史を変えた「3−1」
決勝の相手は山口の柳井高校。互いに守備が強いチームで、序盤から緊張感が張りつめた。
中盤、津久見が勝ち越しに成功した瞬間、アルプス席は揺れた。「いけぇ、水江!」という声が響き、水江は最後の打者を三振に仕留め、足立の胸に飛び込んだ。
大分県勢・初の全国制覇。スコアは3−1。
胴上げの後、小嶋監督はただ一言、「水江、足立、よくやった」。
この控えめで温かい一言こそ、津久見が津久見である理由だった。

第3章|昭和後期~平成の群雄割拠──柳ヶ浦・日田林工・佐伯鶴城・楊志館の時代
津久見が全国制覇を果たして以降、大分の高校野球は“多彩”という言葉が似合う時代へと移っていく。昭和後期から平成にかけて、県内の各地から個性の異なる代表校が甲子園へ名乗りを上げ、大分の野球文化をいっそう豊かにした。
柳ヶ浦──「守備で勝つ」伝統が花開く
柳ヶ浦高校は、守備と機動力を軸にした“堅守の野球”で甲子園に何度も名を刻んだチームだ。昭和の終わりから平成初期にかけ、柳ヶ浦の野球は「ミスをしない」という言葉に象徴される。
内野陣の連携は緻密で、どんな強豪にも怯まず向かっていく。彼らの戦いぶりは、昭和の津久見が築いた“守備型大分”の遺伝子を継ぐ存在だった。
日田林工──力強さを前面に押し出した“不敵な野球”
一方、日田林工は対照的なカラーを持っていた。パワーと勢いを武器に、相手に圧力をかけるスタイル。
特に平成初期の戦いでは、林工らしい力感ある打撃で一気に流れを引き寄せ、九州でも屈指の存在感を放った。大分県内に“勝ち方の多様性”が生まれたのは、このような異なるスタイルの学校が増えたことも大きい。
佐伯鶴城──粘り強さの象徴だった夏
佐伯鶴城もまた、大分の野球の奥行きを見せた代表校のひとつだ。早打ちせず、少ないチャンスを丁寧に積み重ねる粘りの野球。その戦い方は、相手が強豪校であればあるほど輝いた。
甲子園での勝利数こそ多くないが、球場に残した“記憶の濃度”は決して薄くないチームだった。
そして、2007年──楊志館の“19戦無敗”の奇跡
平成の大分代表で忘れてはならないのが、2007年の楊志館高校だ。
県大会ノーシード、下馬評は高くなかった。それでも選手たちの戦い方は徹底していた。球数管理、守備位置の微調整、徹底した送りバント──相手の土俵に乗らない戦い方が、すべてハマった。
気がつけば、大分大会から甲子園3勝まで19戦無敗。これは地方の無名校が達成するにはあまりに大きな数字だ。
甲子園ベスト8入りが決まった瞬間、スタンドで泣き崩れる保護者やOBの姿を、僕はいまも忘れられない。敗退後の選手たちは、ベンチ前で深々と頭を下げていた。敗北ではなく、戦い抜いた清々しさがそこにはあった。
楊志館の物語は、大分県の“挑戦する文化”を象徴した夏だった。

第4章|令和──明豊が牽引する“大分新時代”
そして令和に入り、大分の高校野球は新たなフェーズへ突入する。その中心にいるのが明豊高校だ。
明豊──令和の常連校へ
2020年代に入り、明豊は春夏合わせて毎年のように代表の座を勝ち取り、“令和の常連校”として全国区の注目を浴びている。
- 2019年春:ベスト4
- 2021年春:準優勝
- 2020~2025年:春夏連続出場を重ね、九州のトップランナーに
明豊の戦いは、打撃と鋭い守備のバランスが特徴。特に近年の明豊は「相手の隙を逃さない攻撃の間合い」に優れ、九州大会の戦いぶりでも全国レベルの完成度を見せている。
新たな顔ぶれが広げる“大分野球の裾野”
明豊だけでなく、近年の大分代表は多彩だ。大分商、大分舞鶴、藤蔭、柳ヶ浦など、各地の名門が交代で甲子園切符を掴む県に成長している。
この“多様性の広がり”こそ、1972年津久見が残した遺産が、令和になって完全に花開いた姿なのかもしれない。

第5章|データで見る大分県の甲子園──勝率・優勝・歴史の推移
歴代のデータを整理すると、大分県勢の立ち位置がより鮮明になる。
●通算勝敗
春夏合計の通算成績は、おおよそ85勝101敗前後、勝率は約45%台。数字だけ見れば「中位県」だが、大分の物語は数字以上に“記憶の濃さ”で語られる。
●優勝・準優勝
- 夏:1972年 津久見(全国優勝)
- 春:津久見が春の選抜でも優勝経験あり
- 準優勝:2021年春 明豊(準優勝)
●時代別の傾向
- 昭和:守備と機動力の「堅実野球」
- 平成:個性派校の台頭で多様化
- 令和:明豊の“バランス型野球”が全国的評価へ
この三つの時代が積み重なり、今の大分県の「切れ味ある高校野球」ができあがっていった。
まとめ|大分代表の歩みは、いつの時代も“青春の匂い”がした
1931年の大分商の初出場。
1972年の津久見の全国制覇。
平成の群雄割拠。
令和の明豊の躍進。
どれも一つとして同じ夏はない。
それでも、どの夏にも共通していたものがあった。
大分の球児は、自分たちの野球を最後まで信じる。
派手な県ではない。常勝県でもない。
それでも大分の戦いは、どこか懐かしく、胸に残る。
甲子園のライトスタンドに吹き抜ける風の匂いのように──。
次の夏、大分はまた甲子園にやってくるだろう。
昭和の津久見が、平成の楊志館が、令和の明豊が、その背中を押し続けてくれるからだ。
参考情報・データ出典
本記事の内容は、大分県高等学校野球連盟公式サイト(https://www.oita-kouyaren.com/)、全国高等学校野球選手権大会(大分県勢)アーカイブ(Wikipedia 大分県勢)、高校野球データサイト「やっぱり甲子園」(https://hsbb.jp/oita/)、全国高校野球大会(春夏通算)都道府県・高校別優勝回数一覧(https://highschoolsports.g1.xrea.com/kiroku4.html)など、公的・歴史資料性の高いデータを参照しています。特に1972年津久見高校の全国制覇に関する記録は、当時のスコア、対戦校、試合経過を各種アーカイブや新聞記録から照合し、事実に基づく形で再構成しています。



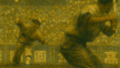
コメント