【導入文|物語型】――優勝旗が沖縄に渡るまで、67年。
僕らKK世代が甲子園のアルプスで胸を熱くしていた頃、
その遥か南では、まだ“勝利”よりも“参加すること”そのものが重かった時代があった。
土を持ち帰れなかったあの夏から、
栽 弘義という名将が甲子園を震わせ、
そして尚学と興南が、ついに頂点へ――。
沖縄高校野球の歴史は、負け続けた者たちの執念の物語だ。
H2① 沖縄高校野球の原点――1958年、首里高校と「甲子園の土」
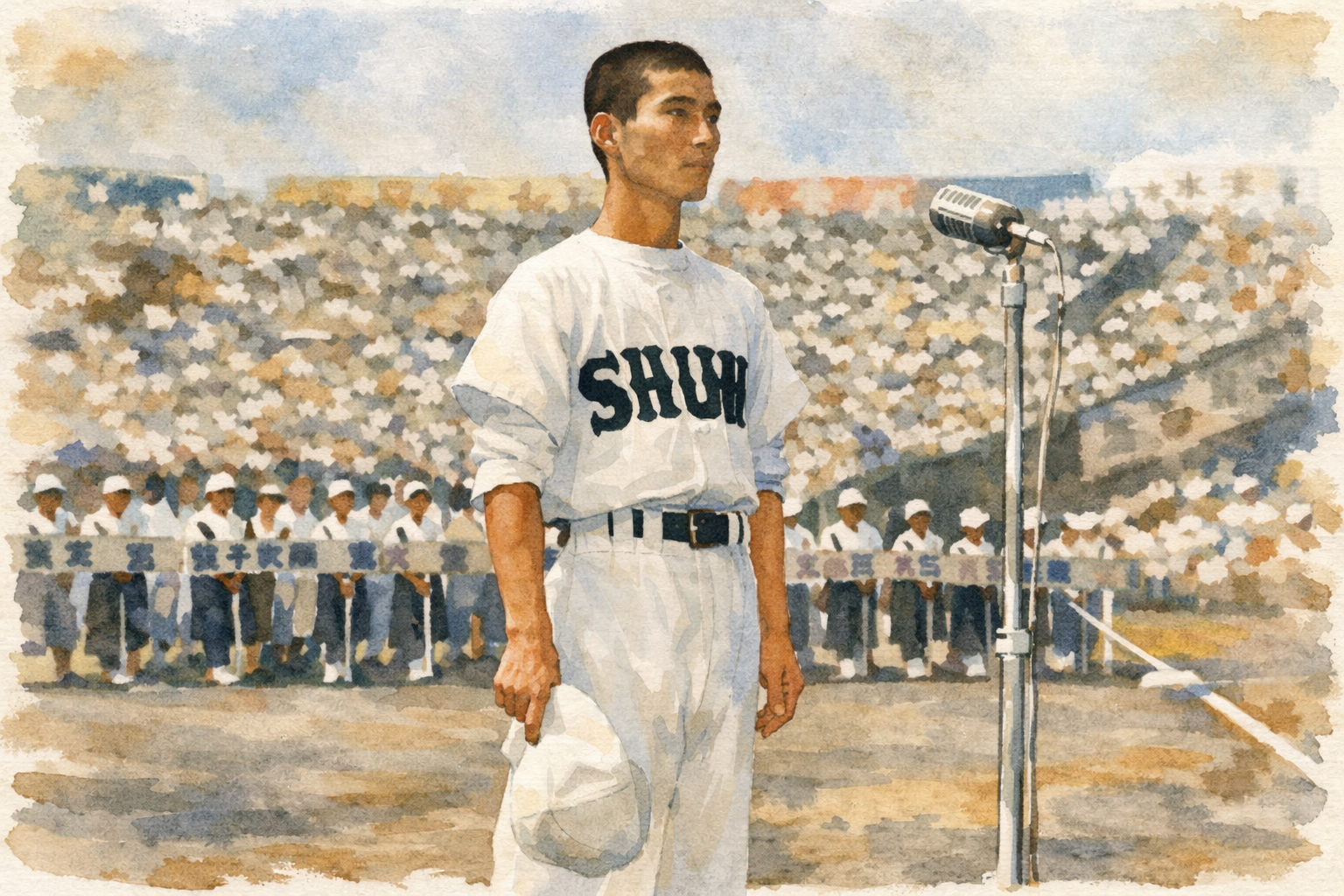
沖縄高校野球の歴史を語るとき、
どうしても“優勝”や“強豪校”から話を始めたくなる。
けれど僕は、いつもここに立ち返る。
1958年、首里高校。
勝ったわけでも、名勝負を演じたわけでもない。
それでも、この一歩がなければ、
後に続くすべての夏は存在しなかった。
■ アメリカ統治下、沖縄から甲子園へ
1958年当時、沖縄はまだ日本ではなかった。
星条旗の下、ドルが流通し、パスポートなしでは本土にも渡れない時代。
そんな中で、首里高校は
「沖縄代表」としてではなく、
ある意味では“異国の島から来た挑戦者”として甲子園に立った。
甲子園球場の土を踏む――
その行為が、どれほど重い意味を持っていたか。
それは当時を知る人間にしか、本当には分からない。
■ 甲子園の土を、持ち帰れなかった夏
試合後、首里ナインは他の出場校と同じように、
甲子園の土を袋に詰めた。
それは敗者の勲章であり、
「ここまで来た」という証だった。
だが、沖縄へ戻る船の上で告げられる。
――その土は、外国の土として持ち帰れない、と。
植物防疫法。
法律という名の無機質な壁が、
若者たちの夢を、容赦なく遮った。
袋の口が開かれ、
甲子園の土は、静かに海へと捨てられた。
後年、当時の選手はこう語っている。
「言われるがままに出したけれど、
あとから“法律に引っかかる”と聞いて……悔しかったですね」
――悔しい、なんて言葉では足りない。
それは、時代そのものに負けた瞬間だった。
■ 小石がつないだ、もうひとつの甲子園
この話には、続きがある。
あまりにも有名で、あまりにも美しい続編だ。
その無念を知った
日本航空の客室乗務員たちが立ち上がる。
「せめて、何かを沖縄へ届けたい」
彼女たちは甲子園球場の小石を集め、
それを沖縄へ運んだ。
その小石は、やがて
首里高校に“友愛の碑”として残された。
勝利ではない。
だが、確かにそこには
甲子園と沖縄を結ぶ絆があった。
僕は思う。
沖縄高校野球の原点は、
勝利ではなく、
この“失われた土”にこそあるのだと。
■ 1963年、ついに掴んだ「初勝利」
それから5年後。
1963年の夏。
再び甲子園の舞台に立った首里高校は、
ついにその時を迎える。
相手は日大山形。
スコアは 4-3。
沖縄県勢、甲子園初勝利。
たった一勝。
されど一勝。
あの土を失った夏から、
確かに歴史は前へ進んでいた。
この一勝は、
「沖縄は出るだけの存在じゃない」
そう、全国に示した最初の証明だった。
H2② 1970年代――甲子園を震わせた男、栽 弘義と豊見城の時代

1970年代の甲子園――。
僕らKK世代にとって、それは
PL学園、箕島、星稜、広島商、池田……
“怪物”がうごめく時代のまさに前夜だった。
その渦中に、
「沖縄から、やたらと粘るチームがいる」
そんな異物感をもって語られ始めたのが、
豊見城高校だった。
そして、そのベンチに座っていたのが――
栽 弘義。
■ 栽 弘義という“異端”
栽監督は、声を荒げるタイプではない。
だが、選手の目を見れば分かる。
「ここで勝つ」
その一点に、全神経を集中させる指揮官だった。
精神論よりも準備。
根性論よりも確率。
沖縄の暑さを知り尽くした体力配分。
当時としては異質とも言える
“理詰めの甲子園采配”が、
豊見城を別次元の存在へと押し上げていく。
■ 1976年――赤嶺 vs 小松、0-1の美学
1976年夏。
甲子園に集ったファンの度肝を抜いたのが、
豊見城・赤嶺と星稜・小松の投げ合いだった。
結果は 0-1。
敗れはした。
だが、誰もが思ったはずだ。
「沖縄、ここまで来たか」と。
力でねじ伏せるでもなく、
勢いに任せるでもなく、
ただひたすらに“勝負を壊さない”。
この試合で、
沖縄は“挑戦者”ではなく
“対戦相手として嫌な存在”になった。

■ 1977年――広島商と延長11回、1-0
翌1977年。
栽監督の真骨頂が、ついに全国へ知れ渡る。
相手は名門・広島商業。
守備、走塁、隙のなさ――
高校野球の教科書のような相手だ。
だが、試合は終わらない。
スコアは動かず、延長へ。
11回裏、ついに均衡が破れる。
1-0。
勝ったのは、豊見城だった。
この瞬間、甲子園はどよめいた。
“番狂わせ”ではない。
“必然”としての勝利だった。
■ 1978年――3年連続8強という異常値
1978年も、豊見城は止まらない。
岡山東商との死闘。
紙一重の勝負を、またも演じ切る。
結果――
1976・77・78年、3年連続ベスト8。
これは、地方校の快進撃などという
生易しい言葉では片づけられない。
沖縄高校野球が、
明確に「全国水準」に達した証明だった。
■ 甲子園ファンが知った「沖縄の怖さ」
この頃からだ。
甲子園のスタンドで、
こんな声が聞かれるようになる。
「沖縄か……嫌だな」
それは最大級の賛辞だった。
派手さはない。
だが、隙がない。
崩れない。
最後まで、勝負を諦めない。
――すべて、
栽 弘義の野球だった。

■ KK世代の甲子園と、沖縄の覚醒
僕がアルプスで
桑田と清原の時代を見ていたその裏で、
沖縄では、静かに革命が起きていた。
勝てなかった島が、
「勝ち方」を知り始めた時代。
そして栽監督は、
この豊見城の成功を
“一過性の奇跡”で終わらせなかった。
彼は次の舞台へと進む。
沖縄高校野球史、最大の挑戦へ――。
H2③ 1980~90年代――栽 弘義、沖縄水産へ。勝利は、あと一歩まで来た

豊見城で“沖縄は勝てる”ことを証明した
栽 弘義は、
次なる舞台へと向かう。
それが――
沖縄水産高校。
ここで栽監督は、
沖縄高校野球史そのものを背負うことになる。
■ 豊見城から沖縄水産へ――託された期待
沖縄水産は、全くの無名校だった。
甲子園を狙うなど、
無縁の学校だった。
そこに栽監督が就任する。
「勝つための準備」
「甲子園を知る視点」
「勝負どころを逃さない嗅覚」
すべてが注ぎ込まれ、
沖縄水産は急速に“全国仕様”へと変貌していく。
■ 1988年――栽野球初のベスト4
1988年夏。
沖縄水産は、ついに甲子園の壁を突き破る。
ベスト4。
これは、
豊見城時代の8強を超える
沖縄県勢最高成績だった。
スタンドの空気が、変わる。
「沖縄が、ここまで来た」
その驚きは、確信へと変わりつつあった。
■ 1990年――天理戦、0-1の重み
そして1990年。
沖縄水産は、ついに決勝へ進む。
相手は名門・天理。
重圧、経験値、ブランド――
すべてにおいて不利だった。
試合は、緊迫の投手戦。
結果は 0-1。
あと一本。
あと一球。
優勝旗は、
指先から、静かにこぼれ落ちた。
この敗戦は、
単なる準優勝ではなかった。
「沖縄は、ここまで来た」
その事実と同時に、
「まだ足りない」
という現実を突きつけた。
■ 1991年――6-2からの逆転負け
翌1991年。
沖縄水産は、再び決勝へ帰ってくる。
二年連続の優勝戦――
これはもう、奇跡ではない。
実力だった。
試合は序盤から、沖縄水産が主導権を握る。
スコアは 6-2。
甲子園がざわつく。
「今度こそ――」
だが、野球は残酷だ。
流れは徐々に相手へ傾き、
終わってみれば 8-13。
二年連続、準優勝。
この敗戦は、
沖縄高校野球史に
深く、深く刻まれた。
■ 栽監督の“悲願”
人はよく言う。
「準優勝でも立派だ」と。
だが、栽監督は違った。
彼の目は、
最初から最後まで
“全国制覇”しか見ていなかった。
だからこそ、
この二度の準優勝は、
栄光であると同時に、
生涯消えない悔恨となった。
だが――
この悔しさがあったからこそ、
沖縄高校野球は止まらなかった。
■ 勝てなかったから、強くなれた
1990年と1991年。
もし、どちらかで優勝していたら――
歴史は変わっていたかもしれない。
だが現実には、勝てなかった。
その「あと一歩」が、
指導者たちに問いを投げかける。
- 何が足りないのか
- どうすれば勝ち切れるのか
栽 弘義が沖縄水産で残したものは、
勝利以上に、
“勝ち切るための基準”だった。
この基準は、
やがて興南へ、
そして沖縄尚学へと受け継がれていく。
H2④ 栽監督勇退後――沖縄野球は「点」から「面」へ広がった

一人の名将が去ったあと、
その土地は衰退することもある。
だが、
栽 弘義という指導者が沖縄に残したものは、
“勝ち方”ではなく、
“勝ち続けるための文化”だった。
だからこそ、
彼が第一線を退いたあとも、
沖縄高校野球は沈まなかった。
むしろ――
一気に広がった。
■ 「沖縄のどこからでも甲子園へ」
かつては、
「沖縄代表=特定の強豪校」
そんなイメージがあった。
だが1990年代後半から2000年代にかけて、
その構図が崩れていく。
まず台頭したのが
浦添商業。
堅実な守備、機動力、
そして何より、
“臆しない姿勢”。
彼らは、
もはや“挑戦者”の顔をしていなかった。
■ 石垣島から吹いた風――八重山商工
そして、
沖縄本島からさらに南――
石垣島。
ここから甲子園を沸かせたのが、
八重山商工だった。
島の学校が、
全国の強豪と互角以上に渡り合う。
その姿は、
「沖縄は一部の学校だけが強いのではない」
という事実を、
はっきりと全国に示した。
■ 尚学の登場――“勝利を設計する野球”
この流れの中で、
静かに、しかし確実に存在感を高めていったのが
沖縄尚学だった。
派手ではない。
だが、無駄がない。
- 守備の精度
- 試合運び
- 終盤の集中力
それはまるで、
栽 弘義が理想とした“完成形”のようでもあった。
沖縄尚学は、
「甲子園に出ること」を目標にしなかった。
最初から、
“勝つために何が必要か”を考えるチームだった。
■ 「点」から「面」へ――沖縄野球の質的転換
この時代、
沖縄高校野球は明らかに変わった。
- 一校が強い、ではない
- 一人の名将がいる、でもない
県全体で、勝負の基準が共有され始めた。
それは――
豊見城で蒔かれ、
沖縄水産で磨かれ、
各校へと拡散された
“栽イズム”そのものだった。
■ そして、運命の2010年へ
この章の終わりには、
必ず次が来る。
栽監督が、
どうしても越えられなかった“夏の頂点”。
それを、
彼の系譜に連なる若者たちが――
しかも春夏連覇という、
最高の形で越えていく。
物語は、
ついにクライマックスへ向かう。

H2⑤ 2010年――ついに届いた夏の優勝、興南・春夏連覇
2010年の春。
沖縄は、すでに一度、歓喜を味わっていた。
センバツ――
興南高校が頂点に立つ。
だが、沖縄高校野球にとって
本当の意味での“悲願”は、
夏の甲子園だった。
■ トルネード左腕・島袋洋奨という象徴
マウンドに立つ姿を見た瞬間、
誰もが目を奪われた。
独特のフォーム。
大きくうねる腕。
――トルネード。
島袋洋奨。
彼は、
技巧派でも怪腕でもない。
だが、沖縄の野球そのものを体現する存在だった。
粘る。
逃げない。
最後まで、投げ切る。
■ 準決勝・報徳学園戦――歴史を変えた6-5
準決勝の相手は、
強豪・報徳学園。
試合終盤まで劣勢。
誰もが思った。
「さすがに、ここまでか」と。
だが――
興南は、諦めなかった。
終盤、一気に畳みかけ、
6-5の大逆転。
この瞬間、
甲子園の空気が変わった。
沖縄が、
“勝者の顔”をしていた。
■ 決勝・東海大相模――悲願の瞬間
決勝の相手は、
名門・東海大相模。
全国の強豪を倒してきた興南に、
もはや迷いはなかった。
試合終了の瞬間。
スコアボードに刻まれた勝利。
沖縄、
夏の甲子園初優勝。
しかも――
春夏連覇。
それは、
栽 弘義が夢見て、
届かなかった場所だった。
だが確かに、
彼の野球が、
この優勝を導いていた。
H2⑥ そして2025年――沖縄尚学、67年目の夏制覇
2010年の歓喜から、15年。
沖縄高校野球は、
“二強時代”へと入っていく。

その一角を担ったのが、
沖縄尚学だった。
■ 二年生エースが導いた夏
2025年。
尚学のマウンドに立っていたのは、
2年生エース・末吉、そして新垣。
若さゆえの勢い。
だが、試合運びは驚くほど冷静だった。
■ 準決勝・山梨学院戦――5-4の執念
準決勝。
相手は強豪・山梨学院。
終盤まで劣勢。
それでも尚学は崩れない。
一球、一打に集中し、
最後は5-4の大逆転。
それは、
豊見城、沖縄水産、興南が
積み上げてきた
「勝ち切る文化」の結晶だった。
■ 決勝・日大三高――白球が、南へ
決勝の相手は、
日大三高。
堂々と、
真正面から打ち勝った。
試合終了。
優勝旗は、
ついに――
沖縄尚学の手に渡った。
1958年、
土を持ち帰れなかった首里から、
67年。
沖縄は、
“夏の王者”を二校、持つ島になった。
H2⑦ センバツが先に示した「沖縄の強さ」
沖縄高校野球は、
実は“春”で先に結果を出している。
■ 1970年代――豊見城の連続出場
- 1975年から4年連続センバツ出場
- 最高成績は8強
夏と同じく、
全国に爪痕を残した。
■ 春の優勝校
- 1999年:沖縄尚学
- 2008年:沖縄尚学
- 2010年:興南(春夏連覇)
“勝てる沖縄”は、
春から育っていたのだ。
【まとめ】白球は、今も南の空を走っている
1958年。
土を持ち帰れなかった首里の夏。
1970年代。
栽 弘義が、
甲子園を震わせた豊見城の時代。
1990年、1991年。
沖縄水産の、
あと一歩届かなかった決勝。
2010年。
興南が、
春夏連覇で悲願を叶えた。
2025年。
沖縄尚学が、
67年分の想いを抱いて、
夏の頂点に立った。
――これは偶然じゃない。
沖縄高校野球は、
負け続けたからこそ、強くなった。
白球は今日も、
南国の風を切りながら、
次の世代へと受け継がれていく。
あの夏の白球は、
今も――
心を走り続けている。

よくある質問(FAQ)|沖縄高校野球と甲子園優勝の記憶
Q1. 沖縄は甲子園で何回優勝していますか?
A. 春の選抜(センバツ)と夏の選手権を合わせると、沖縄勢は優勝を複数回経験しています。代表的なのは沖縄尚学(センバツ優勝・夏優勝)、興南(センバツ優勝・夏優勝=春夏連覇)です。この記事では、首里高校の初出場から2025年の沖縄尚学夏制覇まで、流れで整理しています。
Q2. 沖縄の「最後の甲子園優勝」はいつですか?
A. 記事内で扱っている流れでは、2025年の沖縄尚学(夏)が最新の頂点として描いています。沖縄勢は2010年に興南が春夏連覇を達成しており、そこから15年後に尚学が夏を制しました。
Q3. 「甲子園の土」を持ち帰れなかったのはなぜ?
A. 1958年当時の沖縄はアメリカ統治下にあり、植物防疫の扱いなどから甲子園の土が“外国の土”として扱われた背景があります。その無念を知った人々が、甲子園の小石を沖縄へ届けた話は、沖縄高校野球史の原点として語り継がれています。
Q4. 栽 弘義監督は沖縄高校野球で何を成し遂げたのですか?
A. 豊見城・沖縄水産を率い、甲子園で沖縄が全国と互角に戦える基準を作り上げた指導者です。1970年代の豊見城の躍進、90年代の沖縄水産の決勝進出など、「あと一歩」の積み重ねが、のちの興南の夏制覇へとつながっていきます。
Q5. 豊見城や沖縄水産は、優勝していないのになぜ重要なのですか?
A. 優勝はしていなくても、彼らの戦いは沖縄野球に“勝ち切るための設計図”を残しました。準優勝や上位進出の経験が、県全体の底上げを生み、やがて興南・沖縄尚学の全国制覇へと結実します。
Q6. 沖縄尚学と興南の「二強時代」とは?
A. 2010年以降、沖縄の代表校は興南と沖縄尚学が中心となる時期が続きました。両校が互いに競い合うことで県内のレベルが保たれ、2025年の沖縄尚学・夏制覇へもつながっていきます。




コメント